-
知っておきたい!対処方法
~脳梗塞のリハビリテーション~
新しいリハビリテーションにより機能の回復も期待できるように
-

(1)脳梗塞になった時はどうする!?
-
戦後間もなく、しばらくは日本人の死亡原因のトップだった脳梗塞ですが、その後、予防の周知や治療法の開発などによって減少し、現在はがんや心臓病などに比べると少なくなってきています。しかし、それでも年に約7万人の人が脳梗塞によって亡くなっていると言われています。
もし自分も含めて身近の人が、急に倒れたりしゃべることができなくなったり、片方の手足に麻痺を感じたりした時は、すぐに救急車を呼びましょう。脳梗塞の場合、脳の一部へ酸素を送る血管が詰まったことで症状が現れることが多いため、そうした症状が起こるからです。しかし、脳の神経細胞は多量の酸素を必要とするため、酸素を運ぶ血液が止まると、壊れるまで残された時間は、それほどありません。時間がたてばたつほど、言語障害や手足の麻痺などの後遺症が残る可能性が高くなります。
現在では、脳主幹動脈閉そくが原因で起こった脳梗塞の場合でも、4.5時間以内であれば、点滴で血管内に血栓を溶かす薬品を送り込む血栓溶解療法(組織型プラスミノーゲン・アクティベータ療法:t-PA療法)や8時間以内であれば血管を詰まらせている血栓をカテーテルで吸引して取り出す血管内治療が行えます。なおt-PA療法は、2012年から対象時間が3時間から4.5時間に延び、さらに2005年から健康保険の適用対象となりました。
特に現在のt-PA療法は、新しい薬ができたことで、CTやMRIなどの検査をして病巣が見つかり、また出血も観られないことが確認されれば良好な予後が期待できるようになっています。
ですから、もし自分が倒れたりした時は、意識があるならば、すぐに周囲の人に助けを求めるようにしましょう。周りの人は、助けを求めた人を、できるだけその場で横にしましょう。もし立ち上がったり、歩いたりできたりしても、頭を上げることで脳への血流が悪くなり、脳の障害がさらに悪化する恐れがあるからです。
ただし夏場などは、もし倒れた場所が、太陽が直射する日向であれば、そのままの場所で横になっていると熱中症の危険がありますから、そうした時は、例外的に担架などに乗せて、ゆっくりと日陰に運ぶようにしましょう。
-
脳梗塞のリハビリテーション編
― 脳梗塞の治療法―- 「(1)脳梗塞になった時はどうする!?」
- 「(2)脳梗塞の治療」
- 「(3)早期のリハビリテーションの有効性」
- 「(4)心のリハビリテーションも大事」
-
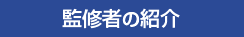
-

正門 由久 氏
<リハビリテーション科専門医>
東海大学医学部 専門診療学系 リハビリテーション科学 教授 -
昭和31年生まれ
昭和57年慶應義塾大学医学部卒業
リハビリテーション医学会専門医、
指導医、認定臨床医
日本臨床神経生理学会認定医
(神経伝導・筋電図、脳波)
米国神経筋電気診断医学会
(専門医、正会員)