-
知っておきたい!対処方法
~脳梗塞のリハビリテーション~
新しいリハビリテーションにより機能の回復も期待できるように
-

(2)脳梗塞になる原因は変わってきている
-
前章で紹介しましたように1960年代に多かった脳梗塞は、小梗塞と言われる「ラクナ梗塞」でした。しかし、その後は、健康診断の普及などによって、ラクナ梗塞の主原因である血圧のコントロールなどが進んだため、その発生数は減ってきました。
それに代わって増えてきているのが、首にある頸動脈や頭蓋内など太い動脈の硬化(アテローム硬化)によって引き起こされる「アテローム血栓性脳梗塞」です。多くの場合、高血圧、糖尿病、高脂血症などによって傷ついた血管壁にコレステロールなどが入り込みアテロームと呼ばれるかたまりをつくって血管を狭くし、そこにさらに血栓などができて血管を詰まらせます。
そして、もう1つが、心臓の不整脈や心房細動などによって心臓内にできた血栓が原因となる「心原性脳塞栓症」です。
心原性脳塞栓症は、心臓内から流れていった血栓により太い血管が突然閉塞するため、病気の起こり方が急激で、ある日、突然に片側の手足が麻痺したり、失語症が現れたりするなど、多くは発症時にいきなり重い症状が現れるのが特徴です
ちなみに脳梗塞の死亡率は、現在は15%ほどですが、問題になるのは、身体の動きを司っている脳が壊死(梗塞)することで、その部分が担っていた働きが制御できなくなる点です。いわゆる「後遺症」が残るわけです。また、最近の脳梗塞は生活習慣などが原因となっていることが多いため、再発率も高くなっています。さらに、特に重度な症状が出た場合は、寝たきりになるなど生活に大きな影響を与えることになるため、普段からの予防が重要になります。

-
脳梗塞のリハビリテーション編
― 脳梗塞は何らかの原因で脳に届く血流量が低下して起こる―- 「(1)脳梗塞とは」
- 「(2)脳梗塞になる原因は変わってきている」
- 「(3)生活習慣病が脳梗塞を引き起こす」
- 「(4)脳梗塞の予兆」
-
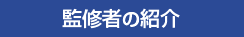
-

正門 由久 氏
<リハビリテーション科専門医>
東海大学医学部 専門診療学系 リハビリテーション科学 教授 -
昭和31年生まれ
昭和57年慶應義塾大学医学部卒業
リハビリテーション医学会専門医、
指導医、認定臨床医
日本臨床神経生理学会認定医
(神経伝導・筋電図、脳波)
米国神経筋電気診断医学会
(専門医、正会員)